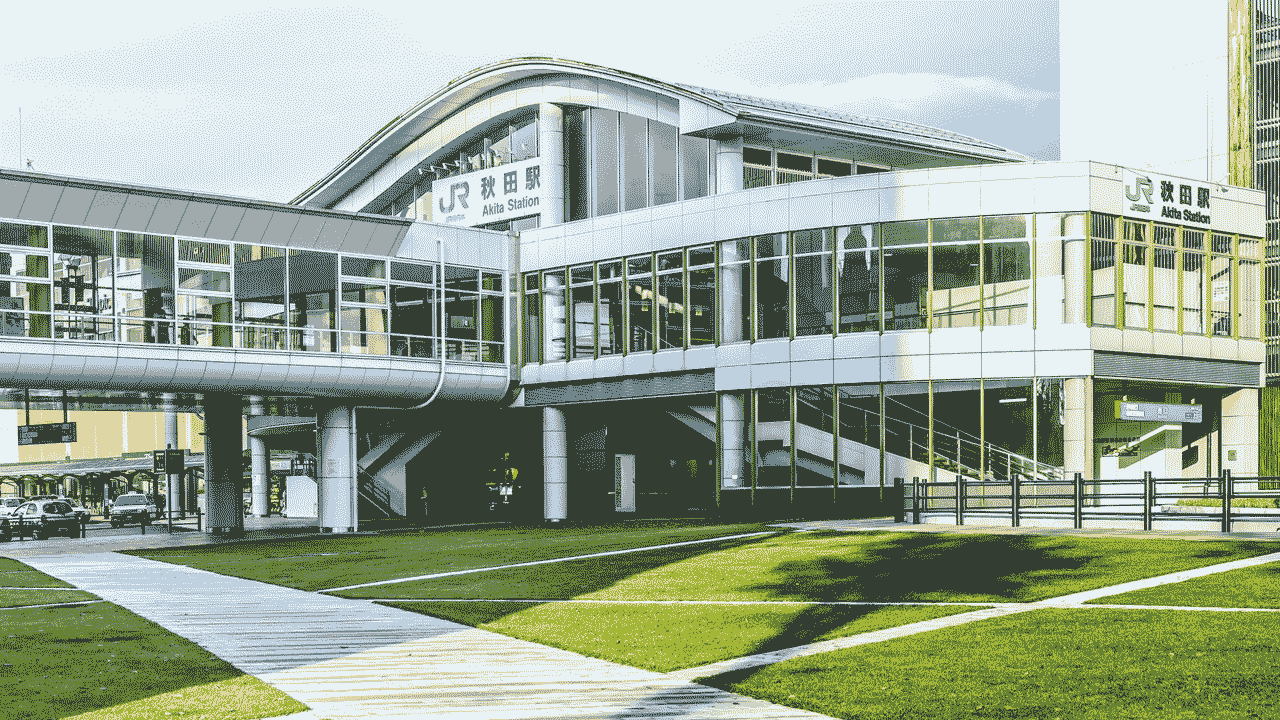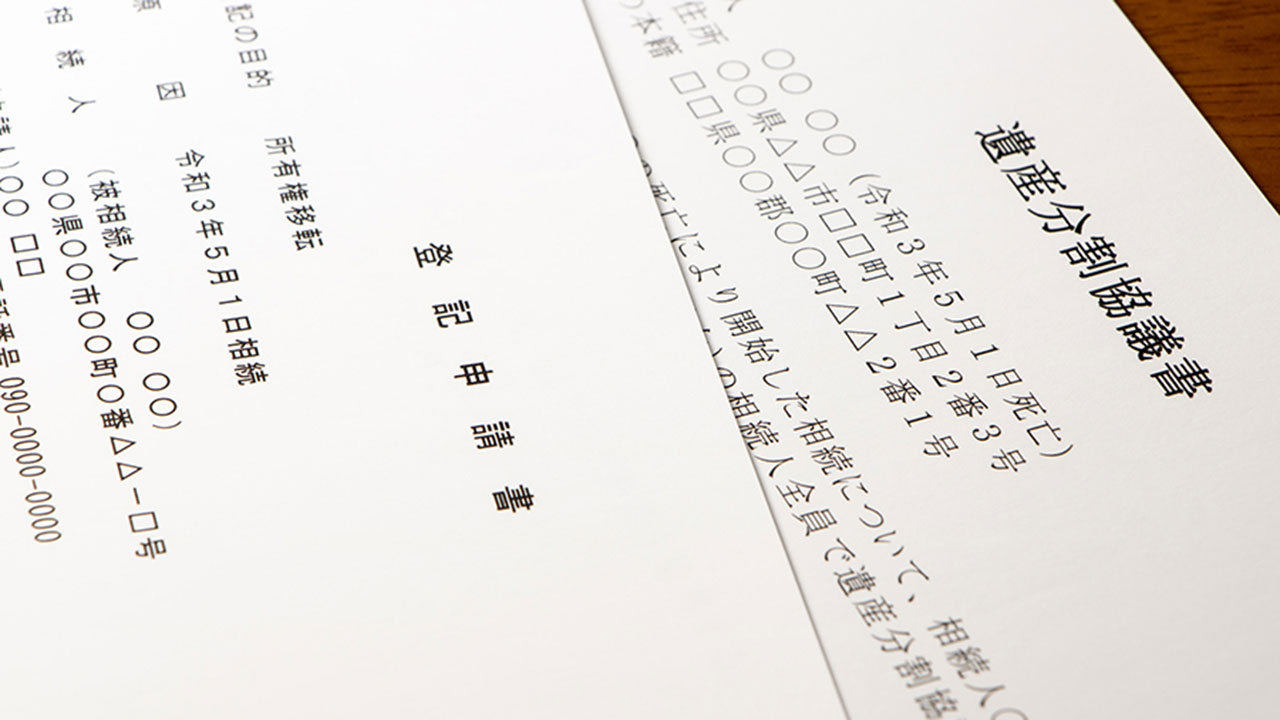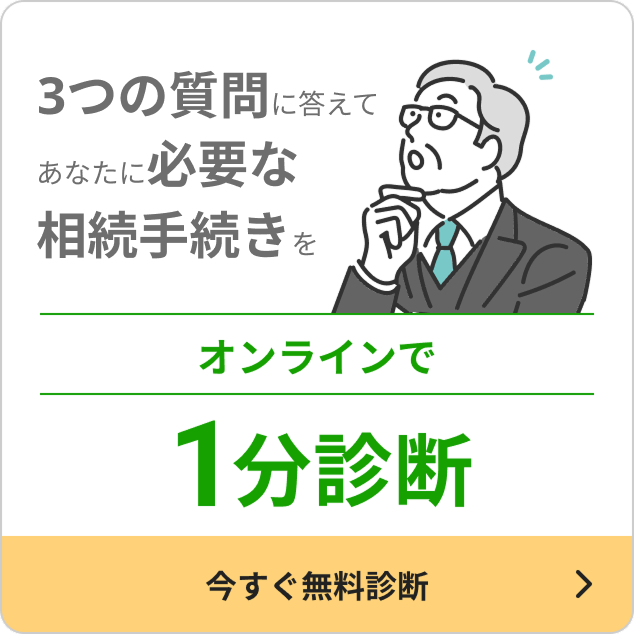土地の評価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例とは?家なき子特例についても解説!
更新日
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/www.sozoku-price.com/navi/wp-content/themes/souzokuhiyou/single.php on line 24
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2023年2月3日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


相続では、預貯金の他に土地や不動産が遺産に含まれているのはよくあるケースです。
土地は高価な遺産です。相続税が気になる方も多いでしょう。
そんな方に是非知ってもらいたいのが「小規模宅地等の特例」という制度です。この特例は、適用されると土地の相続税評価額が最大で80%減額することができます。
この記事では、不動産を相続した方や相続する予定の方へ、この制度の概要や適用要件などをわかりやすく説明していきます。
また、親と同居している方には知ってほしい「家なき子特例」についても解説していますので、是非参考にしてください。

小規模宅地等の特例とは
亡くなった人と生活をしていた人が、相続によって住む場所や事業の土地を失ってしまわないようにという趣旨でできた制度です。
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記の「減額される割合等」の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。・・・
国税庁ホームページ「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
簡単に説明すると「小規模宅地等の特例」とは、一定の要件を満たすことで相続した土地の相続税評価額を50%から80%減額できる制度です。
この特例では、どのような生活をしていて、どのような土地であるのか、という細かい要件が決められており、土地の大きさによって減額の割合が異なります。減額の割合は50%から80%です。
では、どんな要件があるのかをみていきます。
「相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族」
日常の生活費を一緒にしていた場合を指します。単身赴任や学業で離れて暮らしていた場合も、仕送りなどをしていれば生計を一にしていたとみなされます。
「事業の用または居住の用に供されていた宅地等」
小規模宅地等の特例が適用できる土地は、以下の3種類が挙げられます。
- 特定居住用宅地等
- 住宅を建てて居住していた土地
- 特定事業用宅地等
- 事業として使われていた土地(事務所、倉庫、工場など)
- 貸付事業用宅地等
- 不動産貸付業に使用していた土地(賃貸アパートなど)
「その宅地等のうち一定の面積までの部分・・・それぞれに掲げる割合を減額」
小規模宅地等の特例は、土地の種類によって限度面積と減額率が異なります。
| 土地の種類 | 限度面積 | 減額率 |
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
「家なき子特例」とは?
「家なき子特例」は正式名称ではありません。小規模宅地等の特例の中にある「細かい特例」のような位置づけで同居していなかった親族にも小規模宅地等の特例を適用することが可能です。
適用するにはとても細かい要件があり、これらをすべて満たす必要があります。
家なき子とは?
家なき子とはその文字どおり「家が無い」という意味で使われているのではありません。 家なき子特例の要件のうち「相続開始前3年以内に、土地を相続する人は「三親等内の親族」または「相続する人と特別の関係がある一定の法人」が所有する家屋に居住したことがないこと」という部分から「親元から離れて賃貸住宅で暮らしている子ども=持ち家を持っていないひとりで暮らしている子ども」をイメージして「家なき子」と表現されるようになったそうです。
家なき子特例を使える人
家なき子特例には5つの適用要件があります。
- 配偶者及び同居親族がいないこと
- 相続開始前3年以内に、宅地を相続する親族は自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいない
- 相続した宅地を相続税の申告期限まで所有している
- 相続開始前3年以内に、土地を相続する人は「三親等内の親族」または「相続する人と特別の関係がある一定の法人」が所有する家屋に居住したことがないこと
- 相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有したことがないこと
これらの5つの要件を満たすと家なき子特例が適用され、小規模宅地の特例を活用できます。
小規模宅地等の特例の注意点

小規模宅地等の特例は、適用要件の他に以下の注意点があります。
相続時精算課税制度で土地を贈与していた場合
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子どもや孫に生前贈与するときに贈与税を2,500万円までかからなくなる制度です。ただし、その贈与額は相続時に相続財産に加算されます。
被相続人が相続時精算課税制度を利用して贈与した土地は、小規模宅地等の特例の対象外となるので注意が必要です。
被相続人が老人ホームに入居していた場合
自宅での生活が難しくなり、老人ホームなどに転居した先で亡くなるケースも増えています。
そのような場合、相続開始直前に被相続人が自宅ではなく老人ホームに居住していても、以下の一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用されます。
- 被相続人が亡くなる直前において要介護認定等を受けていたこと
- 被相続人が老人福祉法等に規定する老人ホームに入居していたこと
- 被相続人の自宅が生計一親族以外の居住の用とされていないこと
小規模宅地等の特例の申請
自分で相続税の計算をしてみて小規模宅地等の特例を利用したことで相続税額が0円になったとしても、相続税申告書を提出しなければなりません。
必ず必要な書類
- 相続税の申告書
- 遺言書または遺産分割協議書の写し
- 図形式の法定相続情報一覧(被相続人と相続人の関係を証明するもの)
- 被相続人の戸籍謄本(相続発生日から10日以降に作成されたもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 申告期限後3年以内の分割見込書
ケース別の必要書類
相続人の状況や、相続する土地の用途によっては他にも書類を求められます。ケース別に解説していきます。
被相続人と同居していた場合
住民票の写し(相続発生日以降に作成されたもの)またはマイナンバーカード
被相続人と同居していなかった場合
同居していない親族が宅地を相続する場合は、相続発生3年以内に同居していないこと(戸籍の附票の写しやマイナンバーカード)や、賃貸住まいであったことを証明する書類(登記簿謄本や賃貸借契約書など)が必要です。
特定居住用宅地等
個人商店などの事業を行っていた土地であれば、特に書類は必要ありません。
しかし、親族が経営していた有限会社や株式会社など、法人名義の建物がある場合「特定同族会社事業用宅地」とされ、以下の書類が必要になります。
- 対象法人の定款の写し
- 対象法人の登記事項証明書
- 対象法人の株主名簿
貸付事業用宅地等
マンションや構造物のある駐車場、駐輪場などの賃貸事業を行っている土地であれば、特別な書類は必要ありません。
ただし、相続発生より3年以内に新たに被相続人等の特定貸付事業としてその土地を使用した場合、被相続人等が相続発生日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことの証明書類が必要です。この場合、賃貸借契約書や確定申告書を添付して申告します。
まとめ
小規模宅地の特例について解説しました。
ご自身やご親戚などが、相続税申告の際にどんな特例を使えるのかを知りたい場合は税理士に相談しましょう。
相続税の計算には、相続税評価額を正しく算出する必要があり一般の方には難しい部分もあります。
また、申請のための書類を集めるのも一苦労です。これらすべてを専門家に頼むことができます。
「相続費用見積ガイド」では、相続に強い複数の税理士から、一括見積りをもらうことができます。無料で利用できますのでご検討ください。


本記事の内容は、原則、記事執筆日(2022年2月3日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
ご希望の地域の専門家を
探す
ご相談される方のお住いの地域、
遠く離れたご実家の近くなど、
ご希望に応じてお選びください。
今すぐ一括見積もりをしたい方はこちら