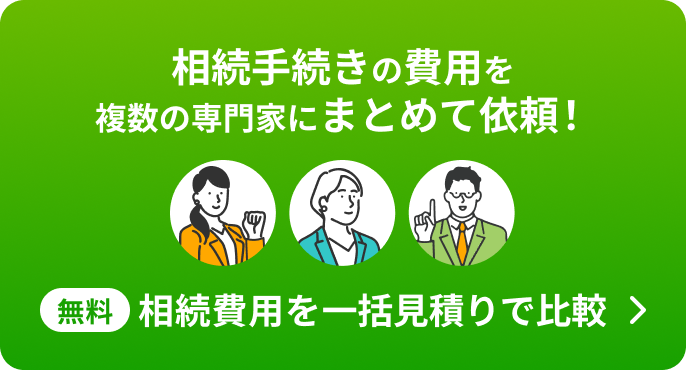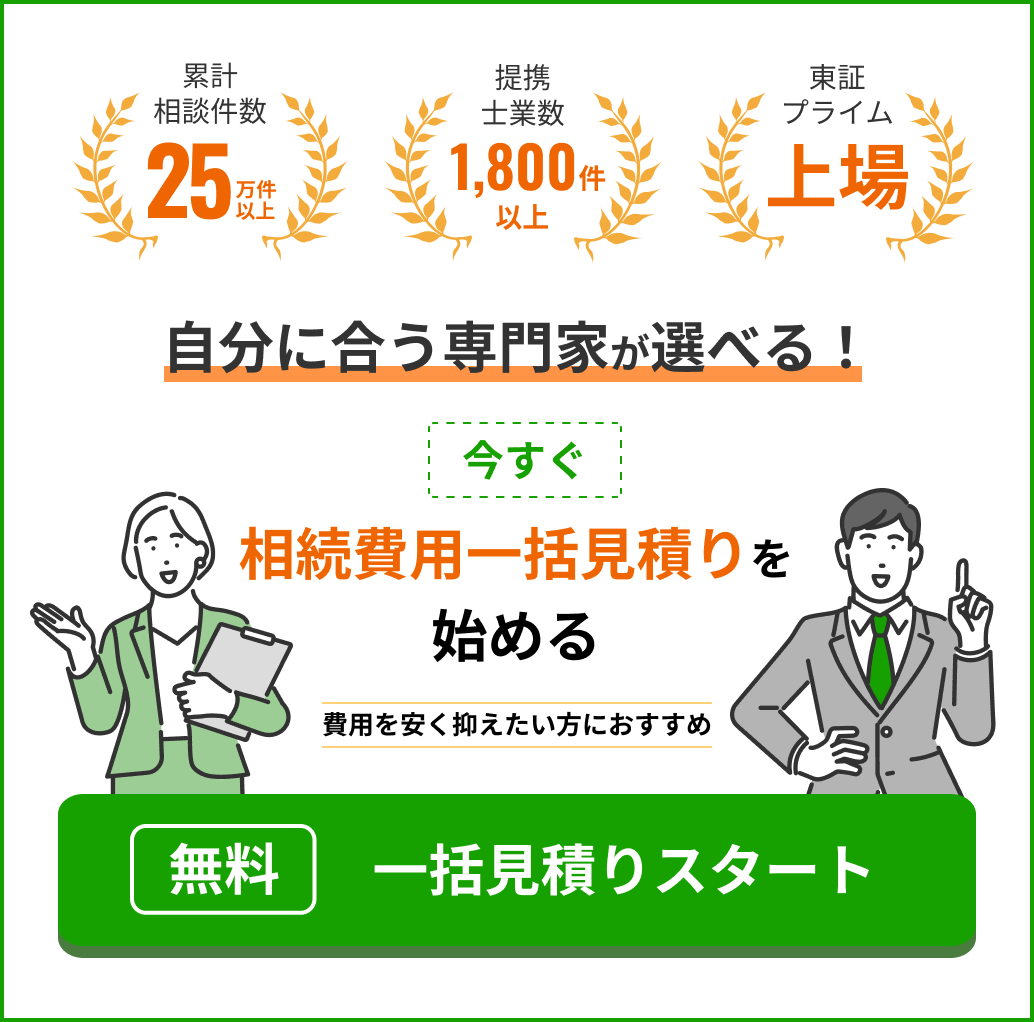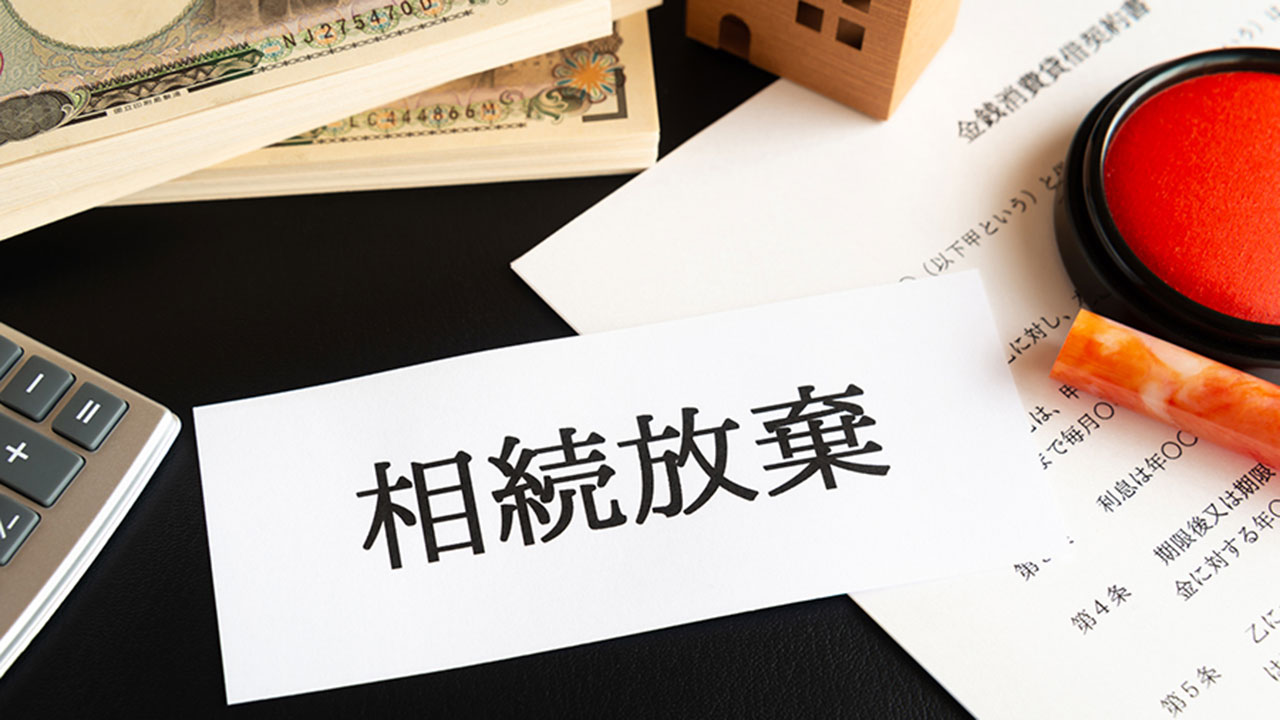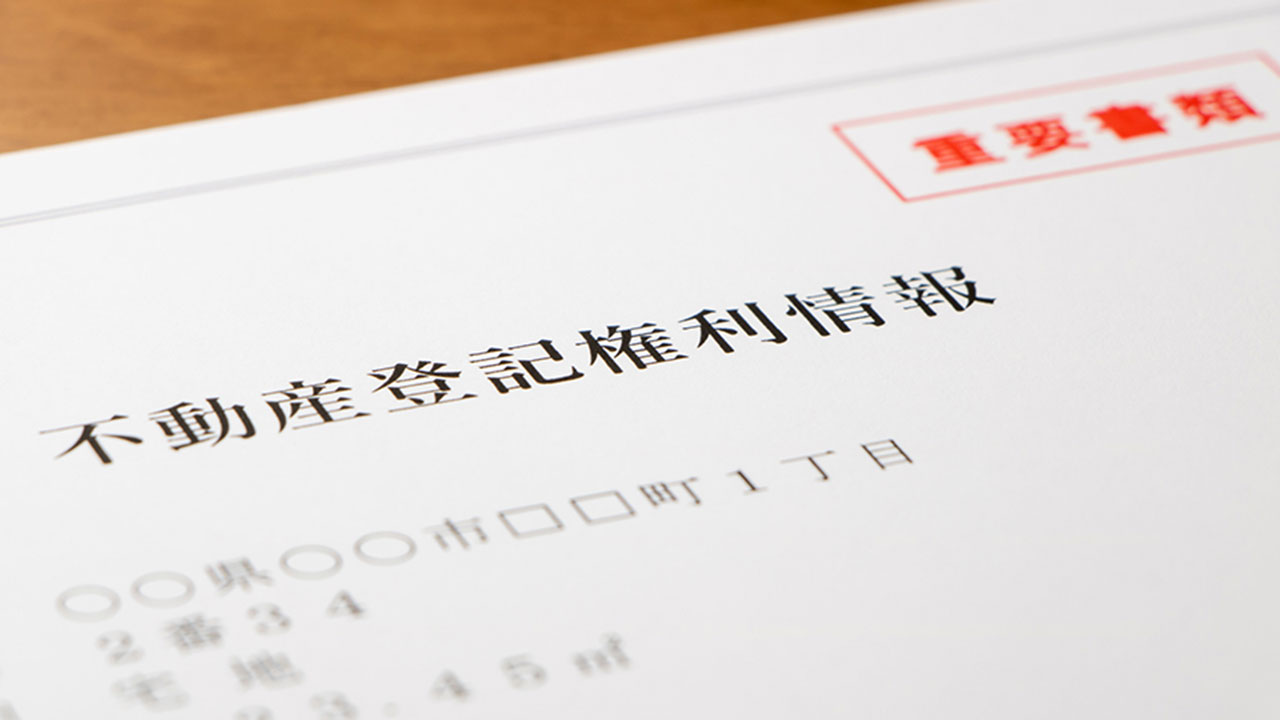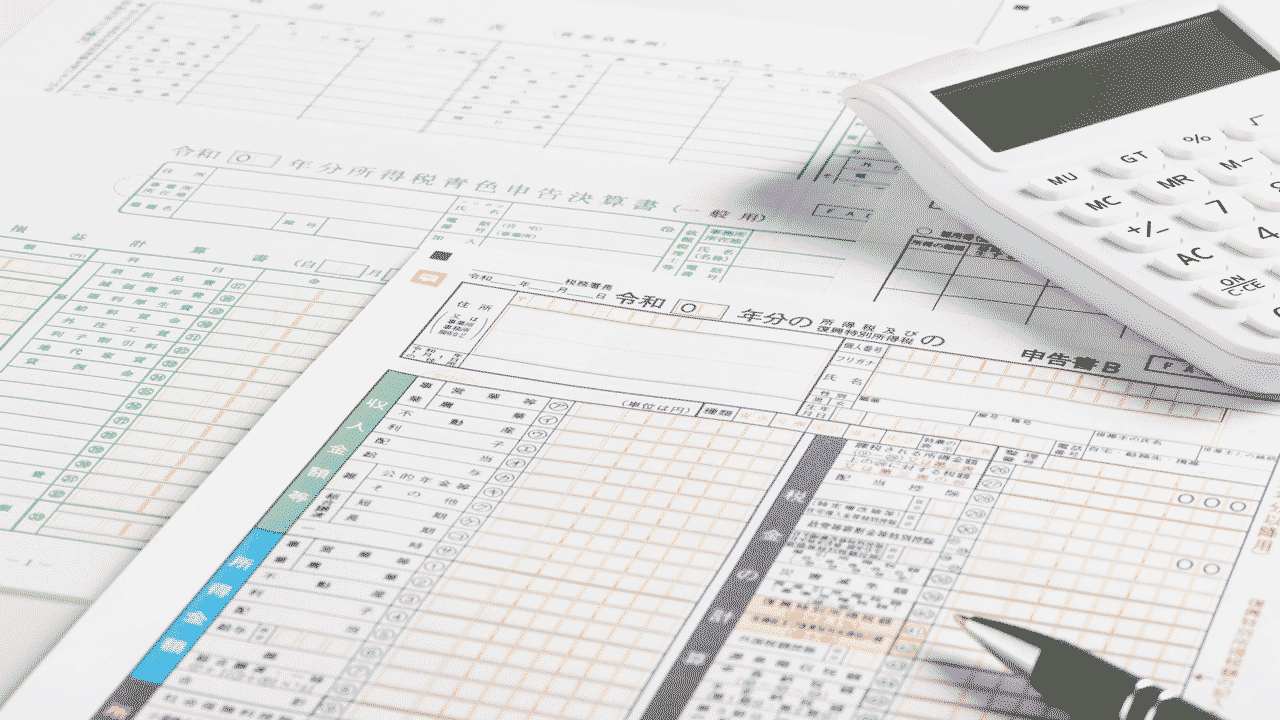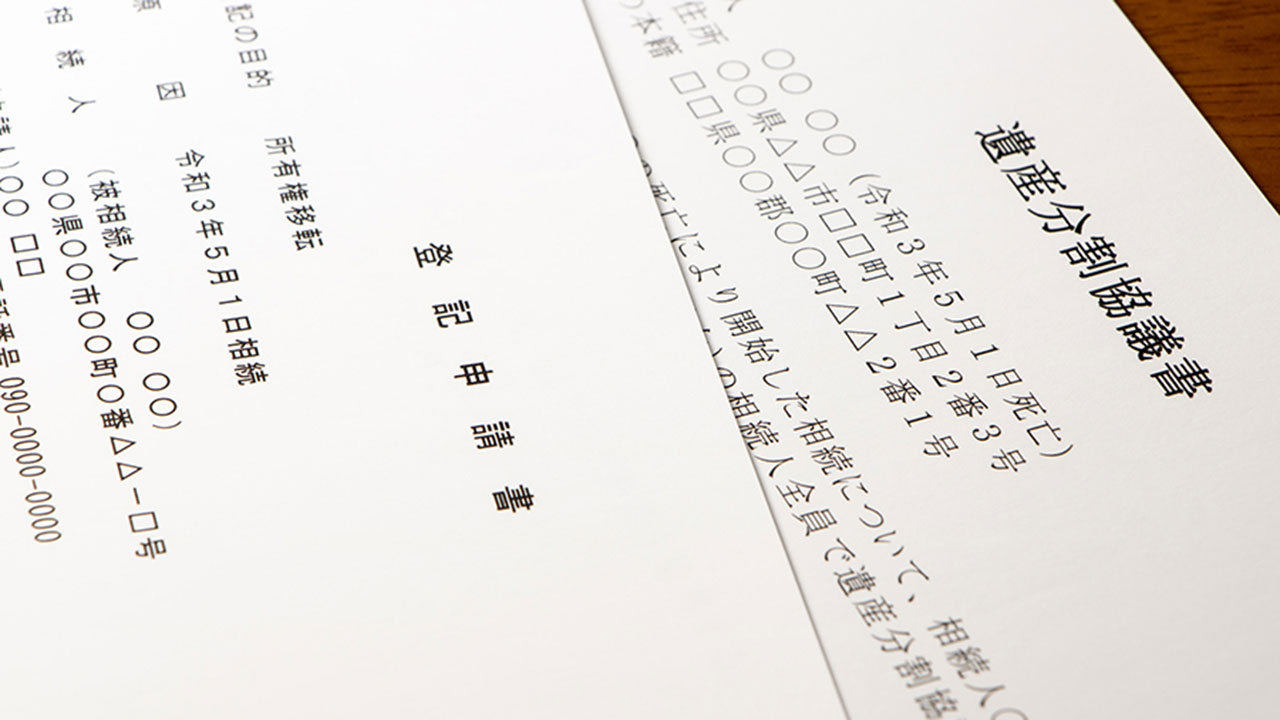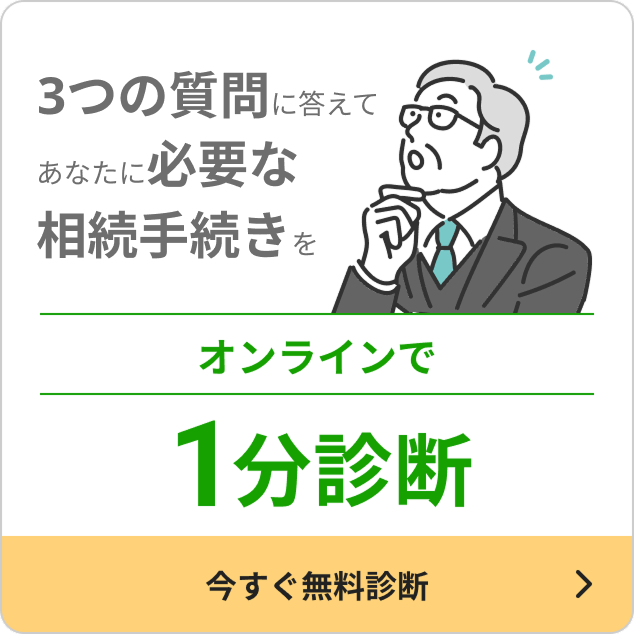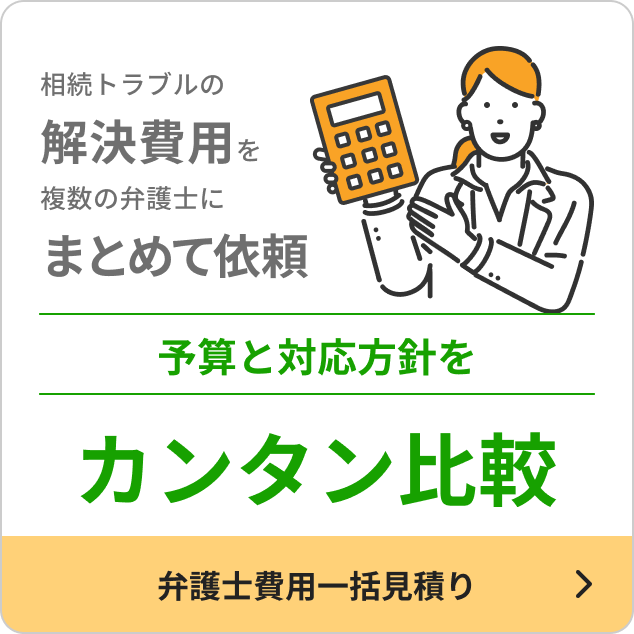相続放棄とは?期限や注意点、手続きの方法など
更新日
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/www.sozoku-price.com/navi/wp-content/themes/souzokuhiyou/single.php on line 24
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2023年1月25日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


家族や親戚の財産を相続する機会はそう多くはないと思いますが、そのとき多額の借金が多い場合はどうすれば良いでしょうか?借金は家族が相続しなければならないのでしょうか?
実は、相続放棄によって借金を手放すことができます。相続放棄とは、故人の財産について相続する権利を放棄することです。
今回は、相続放棄について詳しく解説していきます。ミスなく手続きを済ませるには相続の知識が必須になりますので、ぜひ参考にしてください。

目次
相続放棄とは
相続放棄とは、故人(被相続人)の財産に対する相続権のすべてを放棄することです。
すべてを放棄するので預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄をすると始めから相続人ではなかった扱いとなり、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で必要書類を提出することで認められます。
限定承認とは
相続放棄のほかに相続の方法として、限定承認があります。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。プラスの財産以上にあるマイナスの財産については、切り捨てられます。
限定承認は便利な制度に思えますが相続人全員で申立をしなければならず、手続きも複雑なため、よく検討したうえで限定承認をするかを決めましょう。
相続放棄の手続きができる期間

相続放棄の手続きが可能な期間は、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。この期間を「熟慮期間」といいます。
被相続人と疎遠で死亡の事実をしばらく知らなかった場合は、「死亡を知ったときから3か月以内」となります。
期間を延長したいとき
熟慮期間を延長したい場合は、「相続放棄の期間の伸長の申立」を家庭裁判所におこないます。伸長の申立をした人のみ、延長が認められるため、ほかの共同相続人の熟慮期間には延長しません。
したがって、熟慮期間の延長を希望する相続人が複数いる場合は、それぞれの相続人で申立をおこなう必要があります。
相続放棄をしたほうが良いケース
では、相続放棄を検討すべきはどのケースでしょうか?大きく分けて2つのケースが考えられます。
明らかに負債が多い
相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を放棄します。
したがって両方を比較したときにマイナスが多い場合、相続放棄によって損害を被ることがなくなります。故人に莫大な借金があるときは、積極的に相続放棄を検討しても良いでしょう。
プラスの財産のほうが多いのに相続放棄をしてしまえば、かえって自分が損をしてしまうでしょう。
その他のケース
相続放棄を選ぶ人の多くが、借金などの負債の相続を回避するためですが、その他のケースで相続放棄を検討することもあります。
相続トラブルに巻き込まれたくない
前述のとおり、相続放棄をすることで遺産分割協議に参加する必要がなくなりますから、相続問題が発生しそうであれば相続放棄が考えられるでしょう。
他の相続人に財産を相続させたい
相続放棄をした人が出ると、他の相続人の取り分が増えたり、本来相続権がなかった人が相続権を取得することになります。
例えば、被相続人の配偶者や子どもが全員相続放棄をすれば、相続権は被相続人の親へ、親がいなければ兄弟姉妹へと移っていきます。 したがって他の人に相続権を譲りたいという場合に、相続放棄を検討することがあります。
なお、相続放棄をした人に子どもがいても、その子どもは代襲相続人にはなりません。
また他の相続人の取り分を増やしたいだけなら、必ずしも相続放棄をする必要はなく、自分以外の相続人が財産を受け取るよう遺産分割協議書を作成することで対応が可能ですので、あわせて検討するといいでしょう。
代襲相続とは、本来相続人となる人が既になくなっている場合に、その人の子どもが代わりに相続することです。


相続放棄をすべきでないケース
一方、相続放棄をしなくてもよいケースもあります。そういった場合に相続放棄してしまうと、損したり、後悔することも。よく検討して決めることをおすすめします。
限定承認が有効になる場合
上記のとおり、プラスの財産がマイナスの財産より多い場合、もしくは財産がプラスなのかマイナスなのかわからないという場合は「限定承認」を検討しても良いかもしれません。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と限定承認の違いは以下のとおりです。
| 相続放棄 | 限定承認 | |
|---|---|---|
| 相続権 | すべて放棄 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続 |
| 申述期間 | 3か月以内 | 3か月以内 |
| 申立方法 | 単独で可能 | 相続人全員 |
限定承認は申立から手続きが終わるまでに1~2年かかることもあり、実際に選ぶ人は少ないようです。
相続放棄の手続き方法

相続放棄の手続きについて、解説します。
申述する場所
相続放棄の申述は、被相続人(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所におこないます。
必要書類
相続放棄申述書(全員分)
裁判所ホームページから書式と記入例のダウンロードが可能です。
共通して必要な書類
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
- 申述人が被相続人の配偶者の場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申述人が被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫等)の場合(相続順位第1位)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合(相続順位第2位)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)ですでに死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合(相続順位第3位)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
他の相続人が既に書類を提出している場合は、添付不要です。
費用
相続放棄の申請には、収入印紙、郵便切手代、戸籍関係の書類の取得費用がかかります。そのほか、相続放棄の手続きを専門家に依頼する場合は、専門家報酬がかかります。
収入印紙と郵便切手
家庭裁判所に納める手数料として、800円分の収入印紙を購入します。
また郵便切手は裁判所からの連絡用として使用します。どの裁判所で手続きするかによって異なるので、ホームページなどで確認してください。目安としては1名につき400円程度です。
戸籍関係の書類の取得費用
戸籍の請求にかかる手数料は、戸籍謄本は1通につき450円、除籍謄本は1通につき750円です。
司法書士に依頼したときの費用
司法書士に相続放棄の手続きを依頼したときは、4~7万円程度の費用がかかります。相続人の人数や事務所によっても金額が異なるので、事前に確認しておきましょう。
手続きの期限である3ヵ月を基準に、期限内の手続きを依頼する場合と期限後の手続きを依頼する場合で金額が異なることがあります。
相続放棄の手続きを専門家に依頼したほうが良いケース

相続放棄の申述は、必要書類を揃えて自分でおこなうことができます。しかし、自分で手続きするのが難しい場合や、以下のようなケースでは専門家に依頼したほうが良いでしょう。
- 手続きする時間がなく、期限に間に合わない
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が遠い。面談があったときに行けない
- 被相続人の財産に不明点がある
- 被相続人の財産に価値がわからないものがある
- 必要書類が自力で集められない
- 他の相続人と関わりたくない
専門家に依頼することで、相続放棄申述書の作成や戸籍収集、家庭裁判所への提出までおこなってくれます。
相続費用見積ガイドでは、相続に強い専門家から一括見積が取ることができます。最大5事務所まで見積を取ることができ、費用や対応などを比較することが可能です。
いくつかの簡単な質問に答えるだけで見積依頼できますので、ぜひご利用ください。


相続放棄に関するよくある質問
最後に、相続放棄に関するよくある質問について回答します。
相続放棄は、必ず裁判所に行かなければいけませんか?
相続放棄の申述には、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。これは郵送で申立することも可能です。
相続放棄はいつまでにすれば良いですか?
相続放棄の手続きが可能な期間は、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。相続の開始とは、①相続開始の原因である事実、②それによって自分が法律上の相続人となった事実、の両方を知ったときとされています。
相続放棄をしないと、親の借金は相続人に承継されますか?
3か月以内に相続放棄をしないと単純承認したとみなされるため、親の借金は相続人である子に承継されます。
3か月以内に相続放棄するか決められません。どうすれば良いですか?
相続財産調査が終わらない場合など、3か月以内に相続放棄するか決められない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立をすることができます。
相続放棄の申述は自分でできますか?
自分でおこなうことも可能ですが、少しでも不安があれば専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄をした後に撤回できますか?
原則として、相続放棄をしたあとは撤回はできません。ただし詐欺や脅迫によって相続放棄をしてしまった場合は、撤回・取消ができます。
相続放棄したら、生命保険金は受け取れますか?
原則的に、生命保険金は受取人固有の権利とされているので、受取人に指定されている相続人が相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができます。
まとめ
今回は相続放棄について解説しました。相続放棄の手続きには戸籍や申述書が必要になるため、難しいようであれば司法書士などの専門家に相談しても良いでしょう。
また相続放棄の前に相続財産調査や戸籍収集などが必要になる場合も多いです。やらなければならない手続きを整理して、期限があるものは早めに終わらせましょう。
「相続費用見積ガイド」では相続放棄だけでなく、あらゆる相続手続きに対応できる士業を探すことができます。ぜひ、ご利用くださいませ。


本記事の内容は、原則、記事執筆日(2023年1月25日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
ご希望の地域の専門家を
探す
ご相談される方のお住いの地域、
遠く離れたご実家の近くなど、
ご希望に応じてお選びください。
今すぐ一括見積もりをしたい方はこちら