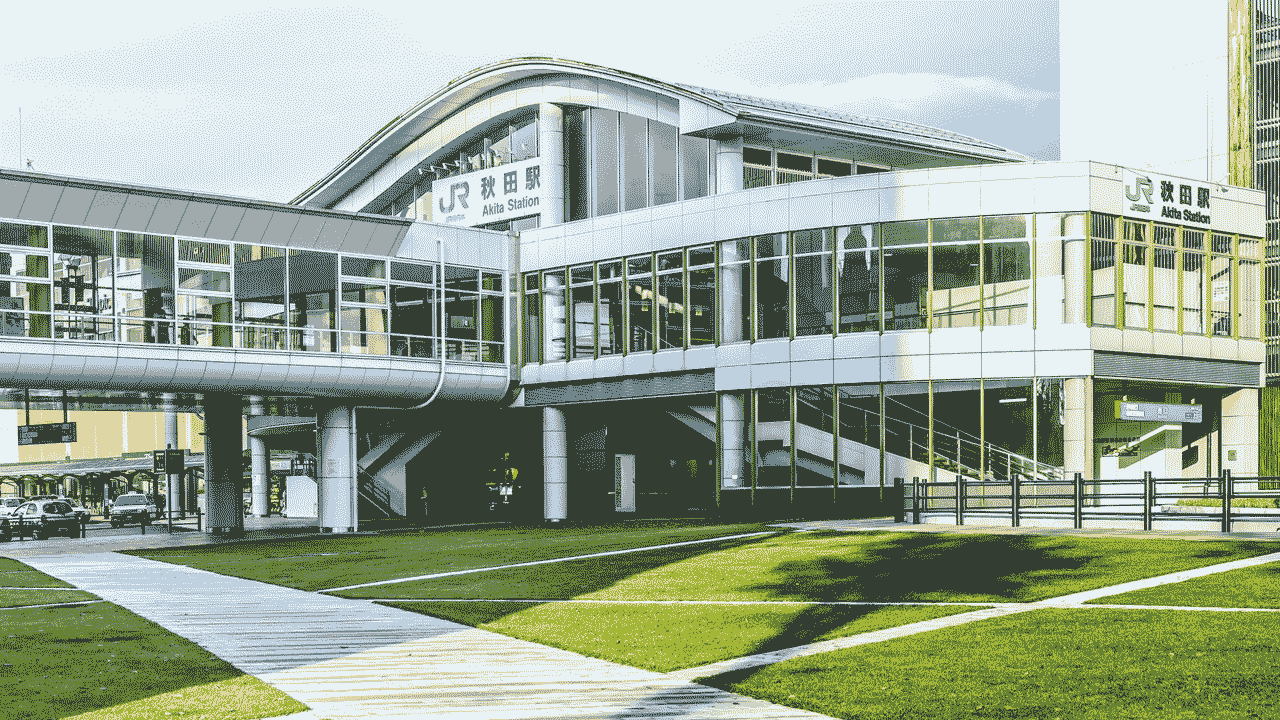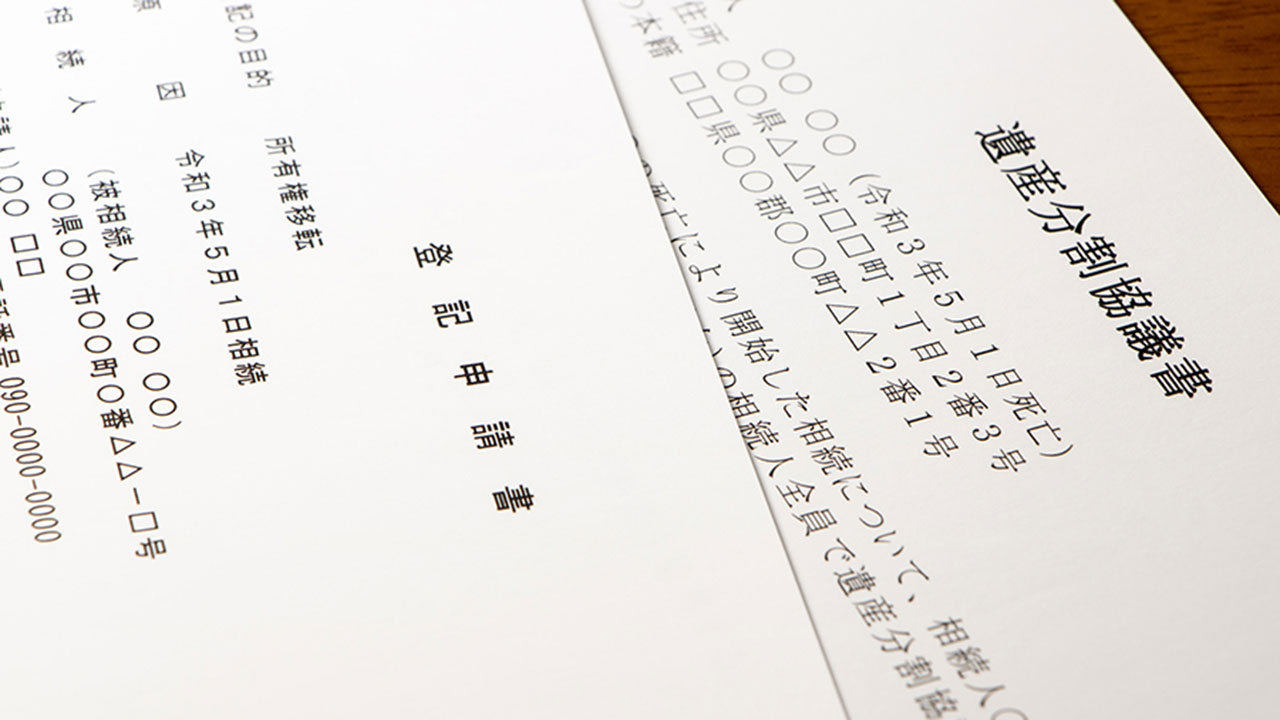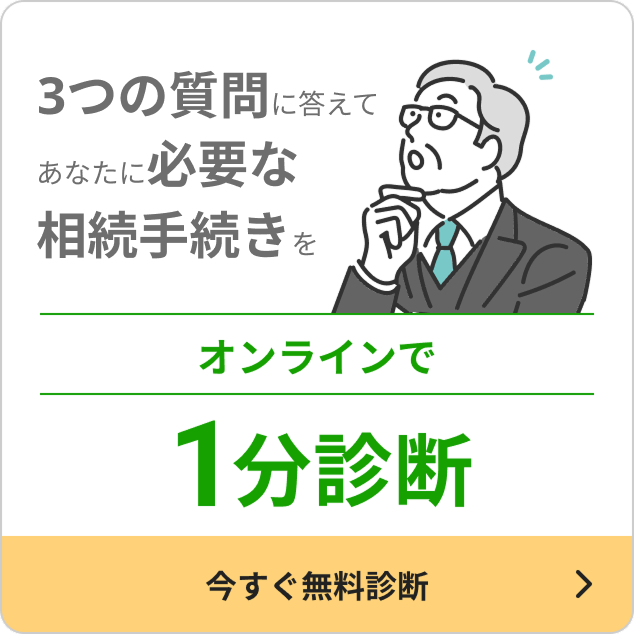【令和5年末まで延長】住宅取得資金贈与の特例とは?メリットやデメリット、要件を解説【行政書士監修】
更新日


「親にマイホームのための資金援助をしてもらいたいけど、贈与税がかかるからなあ…」と考えている方へ、朗報があります。 親が子どもへ住宅購入のための資金援助が非課税になる制度があります。
ちなみにこの制度は令和5年12月31日までと期間が決まっています。利用を検討している人は早めに手続きをしたほうが良いでしょう。しかし、この制度にはメリット・デメリットがあるため、きちんと理解しておくことが大切です。
この記事では「住宅取得資金贈与の特例」について詳しく解説します。ぜひ、参考にしてください。
「住宅の購入を検討している人」「子や孫への住宅資金の援助を考えている人」
この記事のポイント:
- 住宅取得資金贈与の特例により、最大1,000万円まで非課税になる
- 小規模宅地の特例との併用ができないので、どちらが得になるか考える必要がある
- 住宅取得資金贈与の特例を利用する場合は、贈与税申告が必要
この記事の監修者

のばら行政書士事務所
田中友美
〈代表行政書士〉
行政書士法人で勤務後、2018年5月に「のばら行政書士事務所」を開業。相続手続き、遺言書作成支援、許認可申請手続き等を行う。憂いのない相続にするための、終活やエンディングノートについてのセミナー講師実績多数。
事務所ページを見る
住宅取得資金贈与の特例とは?
この制度は、簡単に言うと「子ども、もしくは孫が住宅を購入するための資金援助であれば、一定の金額まで贈与しても贈与税がかからない」というものです。
この特例を利用することで、贈与税の基礎控除である年間110万円とは別に、ある程度まとまった金額を非課税で受け取ることができます。住宅の種類にもよりますが、最大で1,000万円まで非課税になります。
あくまで住宅を新たに取得するための資金援助に限定されるため、既に購入した住宅のローン返済のための資金援助は対象になりません。非課税となる金額は以下のとおりです。
受遺者ごとの非課税限度額(注)
| 贈与の時期・住宅用の家屋の種類 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
|---|---|---|
| 令和4年1月1日から令和5年12月31日まで | 1,000万円 | 500万円 |
国税庁HP、令和4年度税制改正の大綱、税務署発行の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし パンフレットより
(注)非課税限度額
受贈者ごとの非課税限度額は、受贈者が新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の種類に応じた金額となります。
なお、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。
贈与税の基礎控除
贈与とは、無償で金銭を譲り渡し、相手に受諾されることを言います。この個人間の贈与にかかる税金が贈与税です。贈与税は年間110万円までは非課税枠が設定されています。
つまり、年間110万円を超えなければ贈与税はかからず、申告の必要もありません。これを贈与税の基礎控除(暦年贈与)と言います。
贈与税の税率
年間110万円を超えた場合、その110万円を引いた金額に贈与税がかかります。贈与税の税率は金額によって変わるほか、「一般税率」と「特例税率」があり、直系尊属から20歳(令和4年4月1日以降の贈与については「18歳」となります)以上の子・孫への贈与には「特例税率」の低いほうの税率が適用されます。
【一般贈与財産用】(一般税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
【特例贈与財産用】(特例税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
令和5年12月31日までの期間限定の特例
令和3年12月10日に発表された「令和4年度税制改正の大綱」により、住宅取得資金贈与の特例が2年延長され、令和5年12月31日までとなりました。 またそれに伴い、適用要件なども一部変更されました(後述)。


住宅取得資金贈与の特例を受けるための要件

特例を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
受贈者(贈与を受ける人)の要件
- 贈与を受けたときに、贈与者の直系卑属(授与者は直系尊属)であること(養子縁組をしていれば配偶者の父母からの贈与でも適用)
- 贈与を受けた年の1月1日現在で、20歳以上であること(成人年齢の引き下げにより、2022年4月1日より「18歳以上」となりました)
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。ただし、取得する住宅の床面積が40~50㎡未満の場合は、「1,000万円以下」とされます
- 原則として平成21年分から令和3年分までの贈与税申告で「住宅取得資金贈与の非課税」の適用を受けたことがないこと
- 配偶者や親族など一定の特別の関係がある人から取得した住宅用の家屋でないこと。または、これらの人と請負契約により新築もしくは増改築した家屋でないこと
- 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与された資金の全額を充てて住宅の取得や新築をすること
- 贈与を受けた時点で日本国内に住所があり、日本国籍を有していること((注)贈与を受けた時に上記の要件に該当しない場合であっても、一定の要件で対象となる場合があります)
- 贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後、遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
新築または取得する住宅の要件
- 新築または取得した住宅の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住用であること
- 取得した住宅が次のa~cのいずれかに該当すること
a 建築後、使用されたことのない住宅用の家屋
b 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以降 に建築されたもの
c 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合することが、家屋の取得の日前2年以内に、その証明の為の家屋調査が終了、または評価、もしくは保険契約が締結され、次のいずれかの書類により証明されたもの
① 耐震基準適合証明書
② 建設住宅性能評価書の写し(耐震等級に係る評価が等級1,2又は3であるもの)
③ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
- 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、上記のb及びcのいずれにも該当しない家屋で、その住宅用の家屋の取得日までに、その日以降、その住宅用の家屋の耐震改修を行うことについて、下記に掲げる申請書等に基づいて都道府県知事等に申請をし、かつ、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことについて、下記に掲げる証明書等により証明がされたもの
| 申請書等 | 証明書等 | |
|---|---|---|
| 1 | 建築物の耐震改修の計画の認定申請書 | 耐震基準適合証明書 |
| 2 | 耐震基準適合所為梅井申請書(仮申請書) | 耐震基準適合証明書 |
| 3 | 建設住宅性能評価申請書(仮申請書) | 建設住宅性能評価書の写し(耐震等級に係る評価が等級1、2又は3であるもの) |
| 4 | 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書 | 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 |
増改築する住宅の要件
- 増改築後の住宅の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住用であること
- 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している住宅に対して行われたものであり、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること
- 増改築工事に要した費用が100万円以上であること。また、その費用額の2分の1以上が、自己の居住用の部分の工事に要したものであること
住宅取得資金贈与の特例のメリット・デメリット
この制度は人気のある制度で、利用する人も多いです。しかし、メリット・デメリットはきちんと把握しておきましょう。
メリット
まとまった資金を贈与できる
この特例では、暦年贈与ではできない住宅取得のためのまとまった資金を非課税で一度に贈与できる点が挙げられます。また暦年贈与と併用できるのも、大きなメリットと言えるでしょう。
親にとっても、将来の相続財産を非課税で生前のうちに贈与できるため、相続税対策としても効果的です。
3年加算の適用外である
相続開始前の3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合、その贈与はなかったものとされ相続税の対象となります。これが「3年加算」です。
しかし3年加算にならない贈与もあります。「住宅取得資金贈与の特例」は3年加算の対象外なのです。この特例を受けている場合には、贈与者が3年以内に亡くなっても、贈与税の対象にはなりません。
デメリット
小規模宅地の特例が使えない
小規模宅地の特例とは、簡単に言うと「故人が自宅として使用していた土地(もしくは事業をしていた土地、貸していた土地)については、最大8割まで評価額が減額される特例」です。
つまり、一定の要件を満たせば1億円の住宅が2,000万円の評価額で相続できるということです。この特例が利用できるかによって、相続税の金額が大きく変わってきます。
そのため、住宅取得資金贈与の特例と小規模宅地の特例、どちらを利用するとメリットが大きくなるかを考える必要があるでしょう。


住宅取得資金贈与の特例の注意点
注意点としては、住宅取得資金贈与の特例を利用して贈与税が0円になったとしても、申告期限までに必ず贈与税申告をしなければいけないことです。申告をしないと、非課税の適用は受けられません。贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
申告を忘れたとしても贈与の事実は消えないので、税務署に知られた場合は贈与税を払うことになります。さらに無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されます。
まとめ
今回は「住宅取得資金贈与の特例」について解説しました。一度にまとまった金額を贈与でき、最大1,000万円まで非課税になるとても便利な制度です。
しかし小規模宅地の特例が使えない、贈与税申告の必要があるなど、注意すべき点もあります。また相続のときにトラブルになる可能性も。利用するときは家族間でよく話し合い、関係者全員の同意を得ることが必要です。
また、相続対策は住宅取得資金贈与の特例だけではありません。遺言書の作成や家族信託などの選択肢もあります。まずは、専門家に相談してみるのも良いでしょう。
ご希望の地域の専門家を
探す
ご相談される方のお住いの地域、
遠く離れたご実家の近くなど、
ご希望に応じてお選びください。
今すぐ一括見積もりをしたい方はこちら